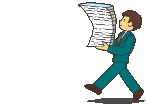社会保険未加入問題
☆建設業の社会保険未加入問題(Q&A)
Q1.社会保険未加入問題とは
(答え)
建設投資が減少し、労働者数も減少しており、不安定な雇用環境にあることから、就業者のうち55歳以上が3割程度、29歳以下が1割程度と高齢化が進行している。このような状況の中、技能労働者の処遇の低さ(賃金、社会保険未加入等)が若年入職者減少の一因となり、産業の存続に不可欠な技能の継承が困難なものとなっていること。
Q2.現状はどうなっているのか
(答え)
建設業において、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3保険に加入している割合は、企業別では87%、労働者別では元請で79%、第1次下請で55%、第2次では46%となっており、職種別では鳶工は47%という状況。
Q3.現場ではどう考えているのか
(答え)
社会保険に未加入の理由は、工事の受注も減少しており、社会保険に加入する経済的な余裕がないことや、職人の社会保険に対する意識が低いとの声がある。また、保険料については、発注者が費用を捻出するよう理解を求めるようにしてほしいとの声がある。
Q4.国はどう考え、どのような施策をとっているのか
(答え)
技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を実現するため、施工現場に対する周知啓発や加入状況の定期把握、加入指導を行い、平成29年度以降は、未加入企業を下請企業に選定しない取扱いとすべきこととし、平成29年度を目途に企業単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当(雇用保険92%、厚生年金保険87%)とすることを目指している。
Q5.社会保険に加入しないとどうなるのか
(答え)
国や都道府県、元請から加入指導を受け、加入しない場合は、社会保険部局に通報され強制加入措置を受けることがあります。また、過去に遡って保険料を追徴されることがあります。
Q6.今から年金を掛けても受給に必要な加入期間25年に満たないので払い損になるのではないのか。
(答え)
年金受給に必要な資格期間は、平成27年10月から10年に短縮されることとなっている。また、年金保険は要件を満たせばケガなどで障害を負ったときの障害年金や本人が亡くなったときの遺族が受ける遺族年金の受給にもつながる。
Q7.社会保険の加入要件とは
(1)雇用保険の加入要件とは
(答え)
労働者が1人でも雇用される場合は強制適用となる。個人事業主や法人の代表者は適用除外となり、また、①1週間の労働時間が20時間未満である者、②継続して31日以上雇用される見込みがない者、③季節的に雇用される者などは適用除外となる。
(2)健康保険、厚生年金保険の加入要件とは
(答え)
法人の事業所に雇用される者及び常時5人以上の個人事業所に雇用される者は代表者も含めて強制適用となる。ただし、①臨時に雇用される者、②季節的に雇用される者などは適用除外となる。
Q8.具体的に何をすればいいのか
(答え)
雇用保険については、管轄のハローワークに、また、健康保険・厚生年金保険については、管轄の年金事務所に相談し、加入要件を確認の上、適正な手続きを行う。
(答え)
建設投資が減少し、労働者数も減少しており、不安定な雇用環境にあることから、就業者のうち55歳以上が3割程度、29歳以下が1割程度と高齢化が進行している。このような状況の中、技能労働者の処遇の低さ(賃金、社会保険未加入等)が若年入職者減少の一因となり、産業の存続に不可欠な技能の継承が困難なものとなっていること。
Q2.現状はどうなっているのか
(答え)
建設業において、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3保険に加入している割合は、企業別では87%、労働者別では元請で79%、第1次下請で55%、第2次では46%となっており、職種別では鳶工は47%という状況。
Q3.現場ではどう考えているのか
(答え)
社会保険に未加入の理由は、工事の受注も減少しており、社会保険に加入する経済的な余裕がないことや、職人の社会保険に対する意識が低いとの声がある。また、保険料については、発注者が費用を捻出するよう理解を求めるようにしてほしいとの声がある。
Q4.国はどう考え、どのような施策をとっているのか
(答え)
技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保を実現するため、施工現場に対する周知啓発や加入状況の定期把握、加入指導を行い、平成29年度以降は、未加入企業を下請企業に選定しない取扱いとすべきこととし、平成29年度を目途に企業単位では許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当(雇用保険92%、厚生年金保険87%)とすることを目指している。
Q5.社会保険に加入しないとどうなるのか
(答え)
国や都道府県、元請から加入指導を受け、加入しない場合は、社会保険部局に通報され強制加入措置を受けることがあります。また、過去に遡って保険料を追徴されることがあります。
Q6.今から年金を掛けても受給に必要な加入期間25年に満たないので払い損になるのではないのか。
(答え)
年金受給に必要な資格期間は、平成27年10月から10年に短縮されることとなっている。また、年金保険は要件を満たせばケガなどで障害を負ったときの障害年金や本人が亡くなったときの遺族が受ける遺族年金の受給にもつながる。
Q7.社会保険の加入要件とは
(1)雇用保険の加入要件とは
(答え)
労働者が1人でも雇用される場合は強制適用となる。個人事業主や法人の代表者は適用除外となり、また、①1週間の労働時間が20時間未満である者、②継続して31日以上雇用される見込みがない者、③季節的に雇用される者などは適用除外となる。
(2)健康保険、厚生年金保険の加入要件とは
(答え)
法人の事業所に雇用される者及び常時5人以上の個人事業所に雇用される者は代表者も含めて強制適用となる。ただし、①臨時に雇用される者、②季節的に雇用される者などは適用除外となる。
Q8.具体的に何をすればいいのか
(答え)
雇用保険については、管轄のハローワークに、また、健康保険・厚生年金保険については、管轄の年金事務所に相談し、加入要件を確認の上、適正な手続きを行う。
| 一人親方 | 株式会社等の法人事業所に勤務する労働者 | 個人経営の事業所 | 法人の代表者 | 個人事業主 | ||
| 常用労働者5人以上 | 常用労働者5人未満 | |||||
| 労災保険 | 特別加入 | 会社で加入 | 会社で加入 | 会社で加入 | 特別加入 | 特別加入 |
| 雇用保険 | 加入不要 | 会社で加入 | 会社で加入 | 会社で加入 | 加入不要 | 加入不要 |
| 健康保険 | 市町村国保 または 建設国保 |
協会けんぽ等。適用除外の手続きにより建設国保に加入できる場合あり。 | 協会けんぽ等。適用除外の手続きにより建設国保に加入できる場合あり。 | 市町村国保 または 建設国保 |
協会けんぽ等。適用除外の手続きにより建設国保に加入できる場合あり。 | 市町村国保 または 建設国保 |
| 年 金 | 国民年金 | 厚生年金保険 | 厚生年金保険 | 国民年金 | 厚生年金保険 | 国民年金 |
当会では、厚生労働省の認可を受けて労働保険事務組合を運営しています。
そのため、上記の社会保険関係のうち、労災保険と雇用保険の加入手続きは、当会に委託していただくことにより代わりに行うことができます。
また、当会に委託することにより、一人親方や中小事業主の労災保険の特別加入もできます。